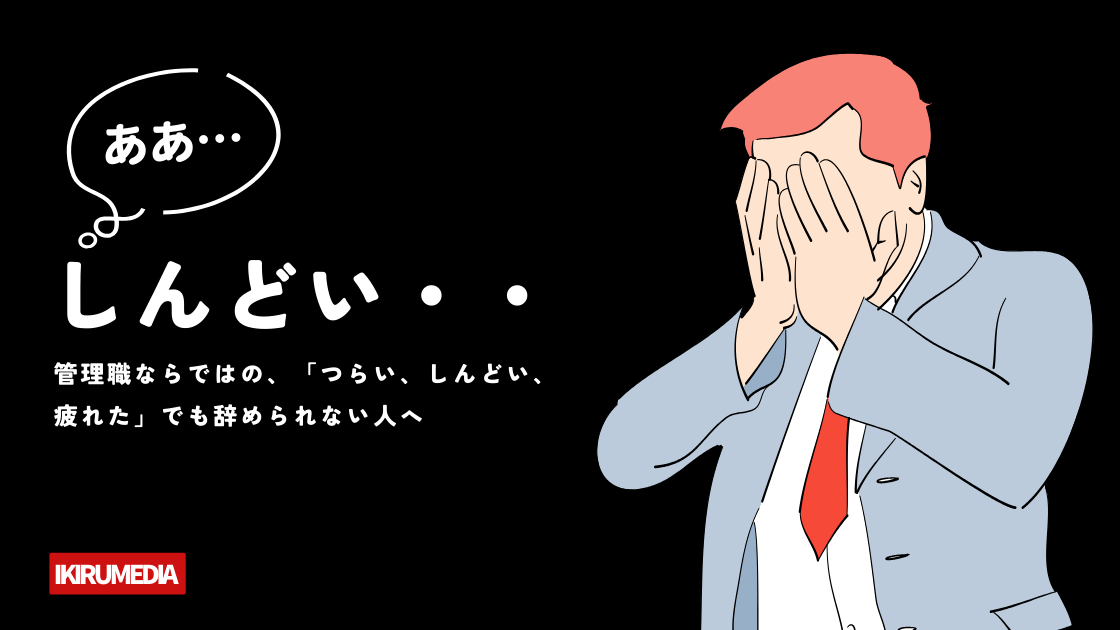
イキルメディアを運営しているKETTY(ケティ)(運営者情報/@ikirumedia)です。
30代~40代の働き盛りの男性に向けて、男性サイドの視点で仕事や生活に役立つ記事を書いています。
管理職になると、「つらい、しんどい、疲れた」の言葉が出てくるようになります。
私も同じように、管理職になってつらく、苦しい毎日を送ってきました。
何が一番しんどいかというと、どんなにつらくても、しんどくても、「会社を辞められないのが一番ツライ」のでは無いでしょうか。
住宅ローンの支払いや、子供を育てるための教育費など、すでに必要な生活費に組み込まれている「お金」があるために、辞めるに辞められない方が多いと思います。
また、多くのブログやサイトでは「会社がツラくてしんどかったら、辞めて転職すればいいんじゃない?」というものが多いですよね。
でも、自分のスキルが世の中に通じなかったり、そもそも地方で転職先が無いという場合は、今の会社に勤め続けるしかありません。
以上は、私のことでもあります。
でも、一方で働き方や、行動、考え方やストレスにきちんと向き合うことで、「勤め続ける選択肢もあるはず」です。
✔ 管理職(次長、課長、課長代理)になってから、ひどく疲れていて、辛くて、しんどい人
✔ 会社を辞めたいけど「お金の問題」で辞めるに辞められない人
✔ 転職先が無く、辞めるに辞められない人
✔ 今の会社に勤め続けるための方法を模索する人
管理職を辞めたいけど、辞められない。
そんな人は、どうやって乗り越えれば良いのか、私と一緒に考えていきましょう。
目次
なぜ管理職が「つらい・しんどい・疲れた」なのか、改めて考えよう

初めに、なぜ「管理職がつらい、しんどい、疲れた」状態になるのか、改めて考えていきましょう。
長時間労働になりがちなこと
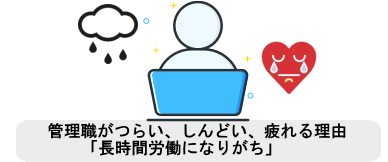
管理職になると、長時間労働になります。
特に異動直後など、慣れない仕事についたばかりの1年~2年目くらいが、長時間労働になりがちです。
管理職になると、上司から「早く帰れよ」という言葉はかけてもらえなくなります。
私もそうでしたが、長時間労働が続くと疲れが取れず、いつかは健康状態が悪化し、破たんします。
だから管理職は、つらいし、しんどいし、疲れるのです。
上司と部下の板挟みであること
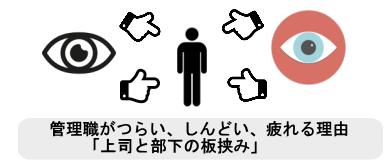
管理職になると、たとえ能力が不足していても「仕事はできて当たり前」「仕事は全部理解していて当たり前」と認識されます。
特に部下にその傾向があります。
例えば、「管理職(次長、課長、課長代理)なんだから、それだけの給料をもらっているし、分かっているんでしょ。」と言うような見方をします。
つまり、どんなに能力不足でも、どんな性格であっても、管理職に対する仕事への要求は高いのです。
一方で、上司(部長など)は、「管理職なので何でも言いやすい」状態になるため、業績や仕事に対する要求が高くなります。
どんなことでも、「課長!あれはどうなっているんだ」「早くしろ!」「自分が忙しいなら部下を使え!」と要求してきます。
管理職は、上司と部下から常に板挟みの状態です。
部下が言うことを聞かない
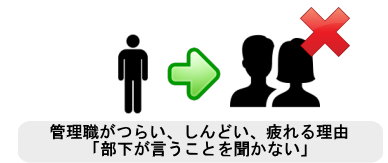
管理職になりたての頃の一番のストレスは、「部下が上司を認めない」ことから、「部下が言うことを聞かない」ことです。
管理職が部署の仕事に精通していれば、部下は管理職の存在を認め、指示を聞き入れます。
ただ、異動したばかりで仕事が分からないときが一番キツイです。
なぜなら、部下に仕事を振ったり、依頼することができず、自分で抱え込むしかなくなるからです。
このような場合、2年~3年もすれば、仕事に慣れると同時に部下があなたの指示を聞くようになります。
ここはガマンの時期とも言えるでしょう。
私の経験でも、部下が異動で少しずつ入れ替わり、自分自身が仕事に慣れてくることで求心力を得ていき、結果、部下が指示や方向性の通りに働くようになりました。
ここまでくるには、しんどくて辛く、疲れる時期とも言えるでしょう。
収入が仕事に対して見合わない
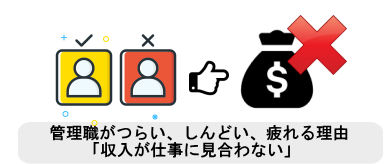
「収入(給料)」は組織によって違いますが、管理職の給料が見合わないことも「しんどい」理由の1つになります。
仕事が苦にならないためには、給料、人間関係、仕事内容の3つのうちどれか1つでも満たされていれば良いのですが、給料も低い、人間関係も悪い、仕事内容もキツイとなれば、大変しんどくなります。
特に管理職は残業がつきませんので、長時間労働をすればするほど、収入が見合わない状態になります。
管理職がツライ、しんどい、疲れるのは、収入が低いことも原因になります。
周りが敵だらけで相談する人がいない
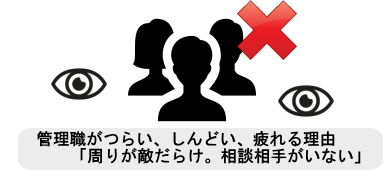
管理職になると、周囲に敵が多くなることに気付かされます。
なぜなら、管理職同士はライバルのような存在になるからです。
自分の部署を守ろうとすれば周囲と上手くいかなくなり、仕事で結果を出せば嫉妬の対象になります。
もう1つは、部下や同僚にも決定的な上下関係が出来てしまうため、本音で相談しても噂が広がるリスクがあります。
心を開いて相談できる相手がいなくなってしまうのが、管理職にとっては辛く、しんどいのです。
本当に追い詰められたときは、公的機関へ相談しましょう。
私も何度か相談しています。
「欲」が無いと管理職はしんどい生き物である
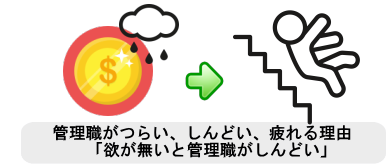
私が管理職をやってみて気付いたのは、「欲」がないと、管理職がしんどくて続けられないことです。
「欲」を良い言葉に替えると、意欲や向上心、目標という言葉に置き換えられます。
管理職に欲が無く、「別に現状維持でいいやー」と考えた途端に、坂を転げ落ちる感覚になります。
管理職になっても向上心や目標を持ち続けないと、現状とプレッシャーに押しつぶされてしまいます。
つまり、欲が無いと管理職はしんどいし、辛いし、疲れる職業なのです。
辞められない管理職の「仕事のやり方・向き合い方」

現代の日本社会では、年金をゴールに会社員の人生を終えることができず、永遠に働かなければなりません。
よほどの資産を持ち、若い頃から資産運用を行っている人はゴールを作れる可能性が高いです。
しかし、資産がなければ、生きるために働き続ける必要があります。
ゴールが無いまま、現在の仕事がツラい、しんどいということは大変苦しいものです。
それは「長く続けられない」ことを意味します。
では、管理職としてどうしたら良いのか一緒に考えてみましょう。
辞められない場合は「細く、長く」働き続ける必要がある

解決方法の1つとしては、「会社員という長い人生を歩んでいる感覚」を忘れないことです。
短距離走でガムシャラに働き続けられるのは、20代までです。
私もそうでしたが、30代以降になると体に無理が生じてきます。
30代後半からは、細く、長くを意識して働きましょう。
年齢を重ねるごとに、1日、1週間、1ヶ月、1年はあっという間に早く終わります。
「着実に1日を終わらせる」という意識で働くと良いと思います。
課題が山積みの場合、目の前のことからとにかく終わらせよう
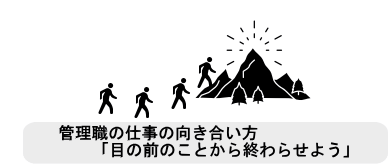
私が管理職になったばかりの頃、部署の中には課題や問題が山ほどありました。
どれから手をつけて良いのかもわからず、知識も経験もない部署です。
以上の場合に限ったことではありませんが、「目の前の仕事に優先順位をつけて片付けていく」のが良い方法です。
「締め切り」が良い例です。
締切日が近い仕事から順に、手をつけていきます。
その間にも、急な仕事やトラブルが入り、優先順位が狂うこともあるでしょう。
長い時間がかかり、回り道に思えるかもしれません。苦しいかもしれません。
でも、一歩一歩着実に前進していくものです。
1年、2年と進めるうちに、必ず差が出るでしょう。
管理職1年目は「仕事が上手く回らないもの」と肩の力を抜いていこう
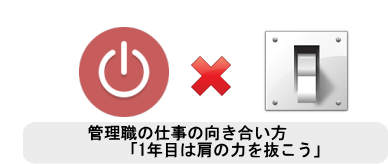
管理職になってすぐには成果が出ません。
自分自身に余裕が無く、仕事もこなしきれないことがほとんどです。
私の場合も、人間関係を把握したり、部下の性格を見極めて仕事を与えるようになるまでに、1年かかりました。
あなたが、管理職になって1年目だとしたら、仕事は回りきらないものと半分諦めてしまうのも1つです。
管理職になったばかりの頃は力が入りすぎるので、「1年間は黙って修行期間だな」と思って、地道に周囲と自分に慣れていくのが良いと思います。
そういう意味では、「半分諦める」というよりは、「肩の力を抜く」というイメージで仕事に向き合いましょう。
自分が働かなくても成果が出るようにしよう
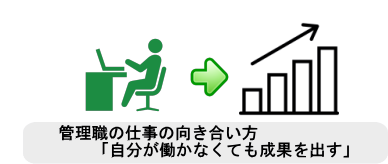
管理職ががむしゃらに働いても、結局は1人の力でしかありません。
私が管理職になって分かったのは、チームで仕事を進めることで、一人よりも大きく成果を出せることです。
また、自分自身が不在でも、仕事が回るようにしておくことも大事です。
「管理職は仕事を抱え込まない」とも言えるでしょう。
自分が働かなくても、誰かが成果を出せるように仕組みを作りましょう。
管理職が枠組みや仕組み、手順を作り、そのレールを走らせることで、成果を出せるようになります。
ちなみにですが、「管理職が働かなくても」というのは、全く何もせず、働かないということではありません。
管理職は、自分しかできないことに集中することで、成果を大きく上げていくことが大事です。
部下のマネジメントのあり方を根本的に変えていく
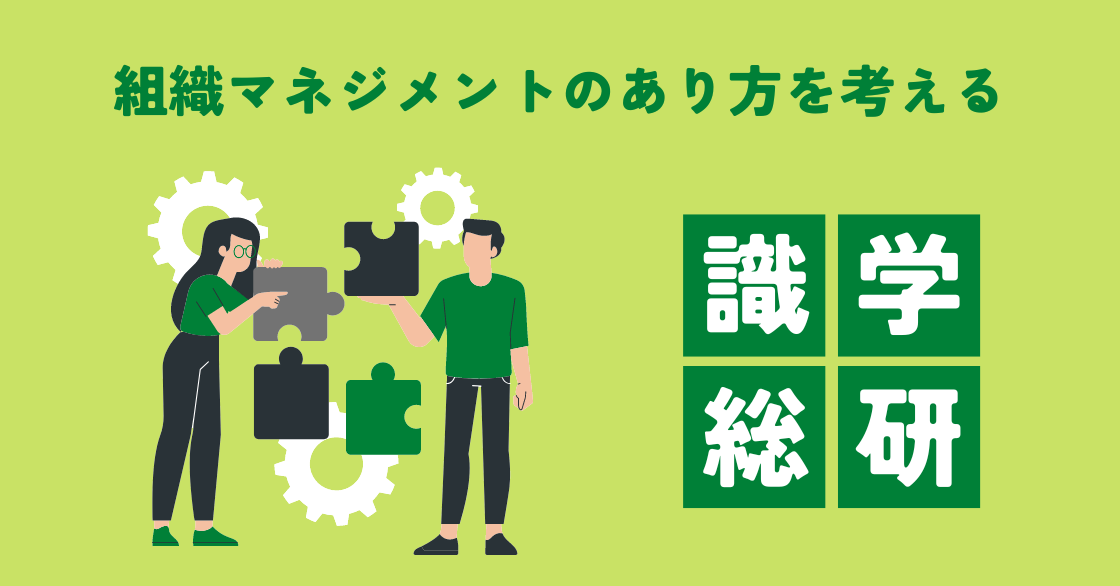
経営コンサルティングの会社 識学が提供するメディア「識学総研」によると、部下のマネジメントのあり方を変えて、管理職がストレスをため込まずに成果を出す方法を解説しています。
3つのポイントで紹介していきましょう。
【識学ポイント1】「感情」ではなく、「理論」でマネジメントする
管理職は、「個人的な気持ちや心情を横に置く」ことがポイントです。
さらに、数字と成果だけを追求することがストレスをため込まない方法の1つです。
私の過去の経験でも、上司の中でほとんど感情がなく、ひたすら結果と成果のみでマネジメントする人がいた記憶があります。
![]() その時は、「なんて冷たい人間なんだ」と思った記憶がありますが、その上司なりにストレスをため込まない方法を自分で確立していたと考えています。今思えば、感情を出さずにマネジメントする方が、誰にも振り回されず、落ち着いてマネジメントができます。理にかなっている方法です。
その時は、「なんて冷たい人間なんだ」と思った記憶がありますが、その上司なりにストレスをため込まない方法を自分で確立していたと考えています。今思えば、感情を出さずにマネジメントする方が、誰にも振り回されず、落ち着いてマネジメントができます。理にかなっている方法です。
【識学ポイント2】部下のモチベーション管理ではなく、成長を促す
管理職は、部下に対してお菓子を渡す、飲み会やランチ会をするということでモチベーションを上げようとする方が多いと思います。
確かに一時的には「雰囲気が良くなる」効果がありますが、絶えず部下のモチベーションを管理するのは難しいですし、管理職がそこまで気を使っていたら仕事で成果は出せません。
良い雰囲気を作ることではなく、部下の成長を促す方がチームの指揮が上がりますので、マネジメントで成果を出すことができます。
![]() 部下とチームをストレスなくマネジメントするためには、部下の中にある内発的・自発的なモチベーションを活用した方が良いでしょう。そのために、部下の成長を促すようにすると、自分で考えながら自走してくれますし、むしろチームの意見交換や情報交換が進み、雰囲気が良くなっていきます。
部下とチームをストレスなくマネジメントするためには、部下の中にある内発的・自発的なモチベーションを活用した方が良いでしょう。そのために、部下の成長を促すようにすると、自分で考えながら自走してくれますし、むしろチームの意見交換や情報交換が進み、雰囲気が良くなっていきます。
【識学ポイント3】部下の意見を聞き、事実を吸い上げてマネジメントに活かす
管理職がストレスをためこまず、成果を出すポイントの3つ目は、「部下の意見に耳を傾ける」ことです。
ポイントとしては、対話をすることではなく、アドバイスをすることでもありません。
部下は、上司に対し、情報を自分の都合の良いように脚色したがるものです。なぜなら、自分の評価にかかわるからです。じっくり部下の話を聞いていくうちに、矛盾点がボロボロ出てきます。
管理職は、脚色された情報ではなく、「事実をしっかりと吸い上げる」ことと「事実を元に判断する」ことです。
以上の識学マネジメントを活用し、ストレスなく業務推進を行っていきましょう。
体を壊すまで働くのは絶対にやめよう
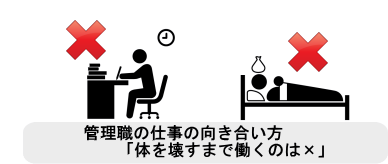
私は管理職になる前に、係長時代に2回体を壊し、管理職になってからも1回体を壊しています。
これは、人員不足の中でガムシャラに働きすぎたからです。
これは、決して褒められることではありません。
なぜなら、収入を得て生活のベースを作るために会社に行っているのに、体を壊して働けなくなったら家族が困るからです。
人生は短距離走ではありません。
体を壊すまで働くのは、絶対にやめましょう。
辞められない管理職の「健康」への向き合い方
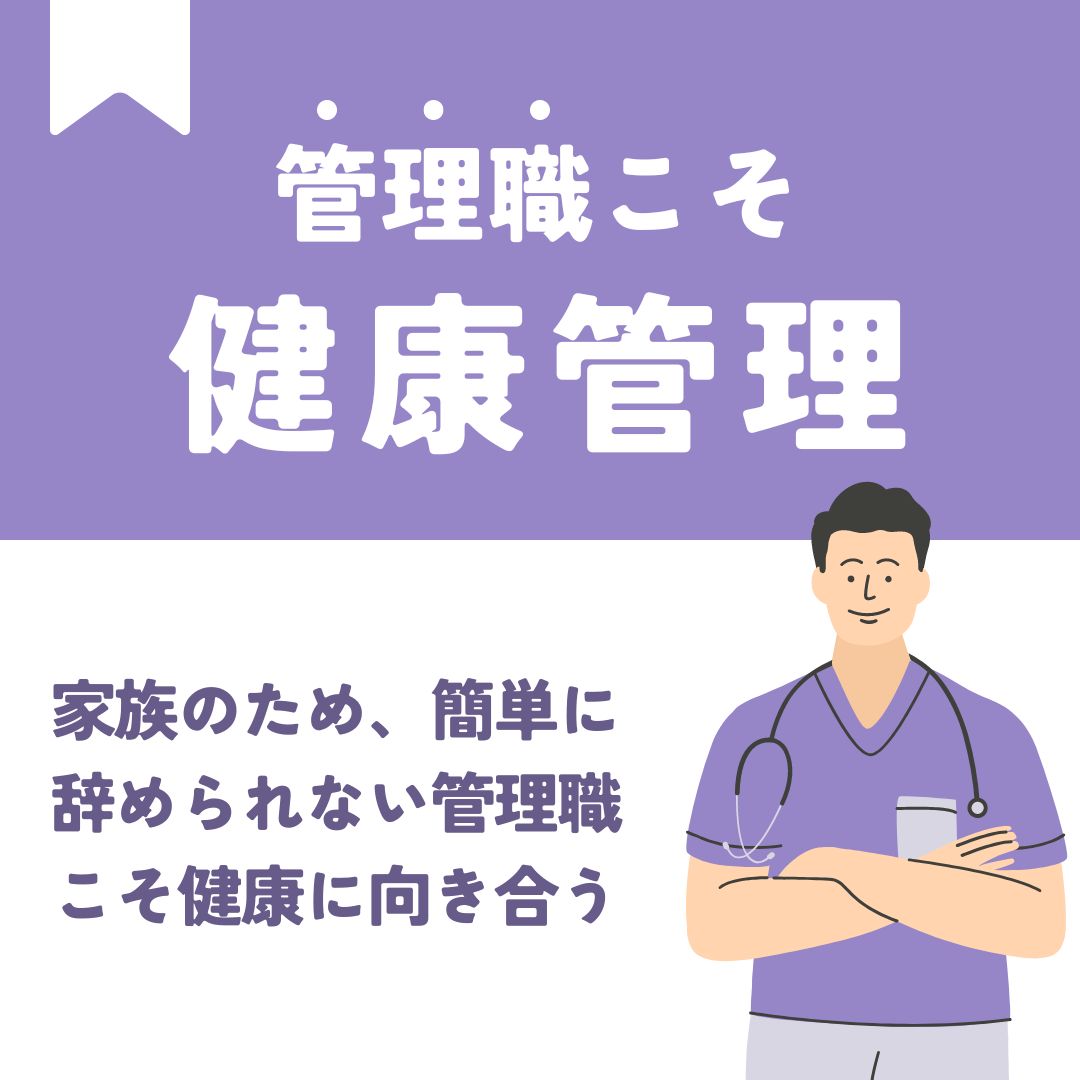
現代の日本社会・経済の状況から考えると、高齢になり、年金をもらう年齢になってもずっと働き続けなければなりません。
その前提として、「健康を維持し続けること」が最重要ポイントになります。
今からでも遅くありません。
ぜひ、健康に向き合ってみましょう。
管理職はストレスを受けたときの自分の変化に注意しよう
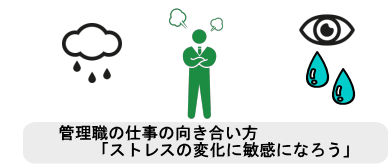
管理職はストレスを受けたときの自分がどう変化するか、よくチェックしておきましょう。
例えば、
・油汗をかく
・まぶたがけいれんする
・声が高くなる
・心臓がバクバクする
など、普段の自分の体と違う感じがしたときは、ストレスに体が反応しています。
男性は特にですが、ストレスの自覚がない場合が多く、いつの間にかストレスを抱え込んでいることが多いです。
ただ、管理職になるとストレスに敏感になっておかないと、体が持ちません。
ぜひストレスによる体の変化を記録して、「自分はどういう時にストレスを感じるか」を覚えておき、ストレス回避をする方法を会得しましょう。
40代でもイキイキする人、30代でも老化が激しい人
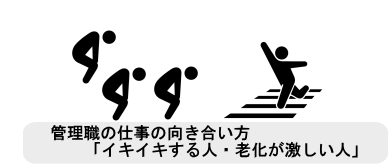
見た目が若いということは、体内の年齢も若く、心も若い人です。
心が若い人は、イキイキ仕事をしています。
イキイキ仕事をしている人は、体力もあり、健康状態も良いです。
健康に敏感な人でもあるとも言えるでしょう。
反対に、30代でも疲れ切った40代後半に見えるような人もいます。
体が疲れていると、精神も悪い方に引っ張られ、体調も悪くなります。
つまり、体調の良し悪しは、健康管理が徹底しているかどうかで決まるものです。
年齢を重ねるほど健康管理をしていかないと、老化がどんどん進行し、脳も老化し、考え方もこり固まった老人になります。
管理職になったら、ぜひ健康管理を意識してみてください。
バランスの良い食事、適度な運動、睡眠、ストレス解消をすると、心も体もきっと若返るでしょう。
家族がいる場合は、必ずリスクヘッジが必要
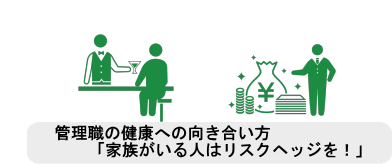
会社員で家族がいる場合は、必ずリスクヘッジを意識しましょう。
会社員のリスクとは、
・収入が減少するリスク
・健康のリスク
があります。
収入が減るリスクは、日本の景気後退によるもので、将来的には正社員として安定的に給料をもらえる状況ではなくなります。
つまり、今後は何らかの方法で自分で稼ぐ方法を身に付けなければ、生活が苦しくなっていくことを暗に示しています。
収入が減るリスクには、副業、アルバイトなどのダブルワークや節約、投資など、収入を増やす仕組みや、減らさない仕組みを作ることです。
健康のリスクとは、健康状態が悪化したり、病気になって「働けなくなるリスク」のことです。
対応としては、保険や共済に入っておくことや、体力をつけるための運動、バランスの良い食事を意識していきましょう。
家族がいるということは、最低限ご飯を食べ、それなりの生活をするために稼がなくてはならないのです。
お金と健康は、ぜひ意識しておきましょう。
「睡眠・食事・運動」には、最大限注意を払おう

管理職のあなたは、30代後半~40代くらいと思います。
年齢を重ねていくほどに、意識してほしいのは、「睡眠」「食事」「運動」です。
1日を精神と体力がベストな状態で過ごすには、以上の3点を意識すると、快適に過ごすことができます。
睡眠は生活リズムを一定にし、毎日ぐっすり眠れるように環境を整えていきます。
寝室は自分が眠りやすい環境を作り、それでも眠れないときは、ストレスなどが関係してきますので、医師に相談すると良いでしょう。
食事は、野菜とたんぱく質を中心に3食きちんと食べます。
運動は、ジムに行き、ジョギングで汗をかき、筋肉を鍛えることで体力がつきます。
体力や筋肉がつき、見た目に自信を持つことで、自分が思っている以上に沢山のことを乗り越えられるはずです。
運動に自信が無い人は、1日20分のウォーキングから始めよう
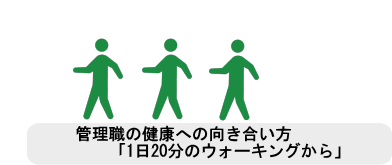
運動が習慣にしていない方は、運動に対する心理的ハードルが高いと思います。
いきなり、ジムやランニング、筋トレと言われても諦めてしまうと思います。
そんなときは、近所を1日20分くらいウォーキングしてみてください。
毎日が無理であれば、1週間に2回でもOKです。
通勤時に歩くのも良いですが、見える景色が狭いので運動自体に意識が向きません。
できれば、プライベートタイムでウォーキングすると良いでしょう。
ウォーキングが習慣になり始めたら、しめたもの。
少しづつ運動が自分の中で「当たり前のこと」になれば、自信がつき、徐々に運動が拡大していけます。
管理職が「ジムへ通うこと」は健康への最大の投資である
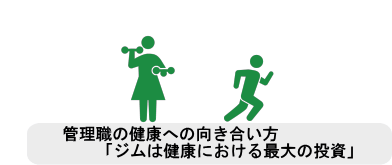
私の経験上、管理職が定期的にジムへ通うことは健康上、「最大の投資に値する」と思っています。
自宅でも筋トレや運動はできますが、ジムの方が運動効率が良く、時間をムダにしません。
管理職は常に時間に追われ、忙しい立場です。
お金を払ってでも、短い時間で効率よく健康を手に入れられるなら、その方が良いとおもいます。
ただ、民間のジムが高額で家計上厳しいようであれば、公的機関は安く利用できると思いますので、ぜひ近くで探してみてください。
辞められない管理職の「休日・休暇編の過ごしかた」

管理職になる頃には、30代後半~40代になっています。
20代や30代前半の頃と違い、体力が衰え、気力もなかなか沸いてこなくなる年齢です。
休日や休暇の過ごしについて、まとめていきましょう。
頭の中から仕事を消し去って、仕事以外の楽しいことをしよう
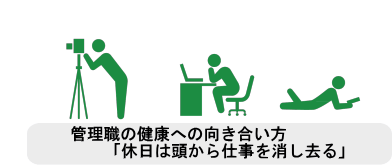
管理職の休日で大事なことは、「仕事のことを考えないこと」です。
頭の中から仕事を消し去って、仕事以外の楽しいことをすることです。
ちなみに、私も沢山の趣味を持っています。
車のDIY修理、バッグDIY修理、ブログ、投資(ソーシャルレンディング、投資信託など)、写真販売や加工修理販売など自分でビジネスをやり、休日をエンジョイしています。
頭の中には、本業の仕事がありません。
ただ、管理職になったばかりの頃は難しいと思います。常に悩みを抱えて苦しい時期です。
ぜひ、頭の中から仕事を消し去って、快適な休日を過ごしてみてください。
疲れているとき、休日は無理にでも休まなければ体は続かないものと心得る
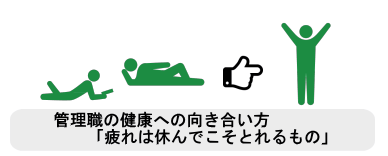
上記とは反対に、平日の仕事で疲れきっているときは、休日は無理にでも休んだ方が良いです。
2日間休みがあれば、1日目は泥沼のように眠るのも1つです。
私も、毎日深夜まで長時間労働をしていたときは、土曜日は朝ごはんを食べてから、すぐに寝て、昼ごはんを食べて寝て、夕ご飯を食べ、すぐに寝るということをしていました。
1日目で疲れが上手く抜けたときは、2日目は好きなことをやりましょう。
そうやって、人生と仕事は上手く回っていくものですから。
体の疲れが取れると、人は勝手に動き出す
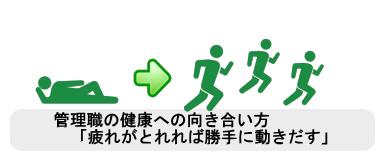
体の疲れが取れると、人間はいてもたってもいられなくなるものです。
「何かやりたいな」「暇だな」と思ったときは、疲れがとれて前向きな状態です。
そんな状態になれば、勝手に体が動きだします。
ぜひ、自分の疲れがとれた状態やタイミングを覚えておくと良いでしょう。
辞められない管理職の「育児・子育て・教育」
管理職になる30代後半~40代頃には、子供が学校に入り、何かとお金のかかる時期です。
子供の育児や子育て、教育はどうやって乗り越えていくか考えていきましょう。
子供が学校を卒業するまでお互いがんばろうと決める
子供が小さい頃は自分の時間が無く、ストレスがたまりがちです。
ただ、大きくなり、小学校、中学校と進むにつれて、今度は教育の悩みが出てきます。
高校、大学になれば、就職への悩みが出てきます。
教育には当然お金がかかりますし、お金を得るには、働かなければなりません。
そこで、夫婦の一旦のゴールを「子供が学校を卒業し、自分で自立するまで」に決めておくと良いでしょう。
転職をあきらめずに活動を続けよう
管理職にとって、ストレスやメンタルで体を壊してしまい、働けなくなることが一番のNGです。
家族を守るために、ひたすら頑張り続けた結果、仕事が出来なくなってしまっては本末転倒です。
そのような中で、より良い環境を求めて転職活動を続けることは、とても大事なことです。
私の10年間の転職活動の中で、どうやったら転職ができるのか、転職を成功させた方法を以下の2記事にまとめています。
辞められないあなたの “新しい風” になれば幸いです。
まとめ
管理職として働く中で、「本当につらい、しんどい、疲れた」「でも、家族がいて、ローンの支払いもあって、簡単に辞められない」という状況は本当につらいです。
私も同じ境遇でした。
管理職の仕事は常に流動的であり、嬉しいこともある一方で、つらいことも多い職業です。
私はつらくなる前に一歩踏み出しておくことを意識しています。
ぜひ、あなたの輝く未来のために、この記事が貢献できましたら大変嬉しく思います。
以上、「管理職が「つらい・しんどい・疲れた」でも辞められない人の人生対応術」でした。
ではまた^^
この記事を書いた人

「生き方」×「働き方」を学び未来を切り開くwebメディア「イキルメディア」の運営者。金融機関や企業の経営企画マネージャーを経て、起業。webメディア運営や出版などを通じてキャリアアドバイスをするなど、事業に邁進しています。
課長・管理職の役割や仕事術をまとめたページを作りました!
部下や上司との人間関係、問題やトラブル、課題、新規事業、人材不足による長時間労働など、多岐にわたる問題にお役立ていただければ幸いです。
(※この記事も掲載しております。)

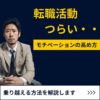

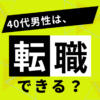





コメント
こんにちは。
上司と部下の板挟みはやはりつらいことが多いですよね…。
休日にどれだけリフレッシュするかが大切だと思いました。
コメントありがとうございます。
休みにどれだけリフレッシュできるかが、今後の人生楽しく生きれるかと思っています^^